2023-5-16
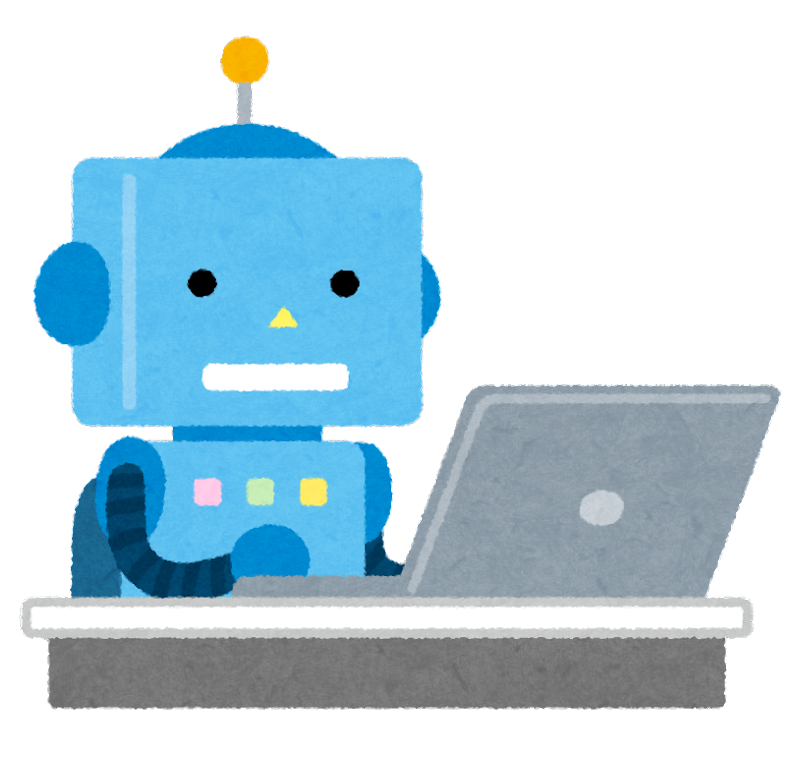
最近毎日のように新聞トップに人工知能AIの記事が出ています。
少し前には、メタバースが話題を呼んでいましたが、なかなか盛り上がらずひとまず熱は一段落しそうです。やはりまだVRグラス等の機器がまだ未成熟なのが原因だと思われます。ただ決して終息した訳でなく、これから何度もブームは訪れるのでしょう。
それより、今は進化した生成系のAIが話題の中心です。
思うに、我が日本がデジタル化に乗り遅れたのは、我々70歳代やその少し下の世代がまだ力を持ち、社会のデジタル化を牽制しているからかも知れません。
それならぜひAIとは何か、その概略を理解してみたいとAmazonを漁ってみました。「洋書」でAIで検索すると、画像生成系のAIが生成したあり得ないグラマラスな若い女性の画集ばかりで(笑)、やっと見つけました。AIはまだ始まったばかりで、書物が出てくるのはこれからでしょう。
そこでご紹介です。私が見つけた本ですが以下の2冊です。以前新聞広告にも載っていた記憶があります。
アメリカではベストセラーとなった、「Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans」(Pelican Books)という本です。(因に英語多読はまだ7歳レベルの本を読んでいて、進みません。英語的には結構高度です。)
日本語版もあり、「教養としてのAI講義」(日経BP)という書名となっています。女性の著者で、一般むけにAIの概略を分かりやすく解説した本のようです。大まかな原理や問題点、哲学的問題など幅広く書かれているようです。実はまだ買っていないのですが、紹介した以上買わざるを得ませんね。
私は「積ん読」の傾向が強いので、しばらくは机の横に置いておく事になります。なかなか理想的な本だと思います。
シニアもこのあたりの本をぜひ理解して、現代人として生きて行きませんか?
(KNK)
《著作権情報》
●教養としての AI講義
2021年2月15日 第1版第1刷発行
2021年10月22日 第1版第2刷発行
著者 メラニー・ミッチェル
訳者 尼丁千津子
解説 松原仁
発行者 村上広樹
発行 日経BP
発売 日経BPマーケティング〒 105-8308 東京都港区虎ノ門43-12
装丁 小口 翔平+三沢稜(tobufune)
制作 岩井康子(アーティザンカンパニー)
翻訳協力 株式会社リベル
編集 田島篤
印刷・製本 図書印刷株式会社
●Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans
PELICAN BOOKS
Penguin Books is part of the Penguin Random House group of companies whose addresses can be found at global.penguinrandomhouse.com.
Penguin Random House UK
First published in the USA by Farrar, Straus and Giroux 2019
First Published in Great Britain by Pelican Books 2019
Published in paperback 2020
008
Copyright © Melanie Mitchell, 2019
Book design by Matthew Young Set in 10/14.66 pt FreightText Pro
Typeset by Jouve (UK), Milton Keynes Printed and bound in Great Britain by Clays Ltd, Elcograf S.p.A.
A CIP catalogue record for this book is available from the British Library
Penguin Random House is committed to a sustainable future for our business, our readers and our planet. This book is made from Forest Stewardship Council™ certified paper.
www.greenpenguin.co.uk

USIさん、全くの同感です。AIでは「重要な戦略・政策決定の判断としては物足りない」と。難しいのは、人類にとって何が「重要な戦略・政策」なのかを(人? AI?)判断するかだろうと思います。このベースを間違ってしまうと人類は破滅に向かうのでは?それこそUSIさんのご指摘SFの世界に飛び込んでしまうのでしょう。この世界に入り込んだら、抜け出せない。私はこれからの事、次の事に期待しています。人とAI(ものすごいスピードで進歩するも)は融合しながら正道を見つけていくことです。(MYZ)
ChatGPTなどに関するAIの最新の機能や、危惧される問題点に関して関心が集まっています。ここでは、KNKさんの記事、MYZさんのコメントに対して私(USI)の意見を述べさせていただきます。
約10年前にスパコン「京」関連の仕事に携わっていた時、情報系の先生方とも付き合いがありました。その中でビッグデータのデータマイニングを専門とされている教授から情報をいただいたことがあり、将来有用な知見が得られるものと考えていました。1980年台頃だったでしょうか、パソコン機能の爆発的な向上を横目で見ながら、限定された機能を搭載したマイコンが家電や色々な機器に搭載されて私たちの生活が便利になりました。ここで私たちは「計算速度や記憶容量の向上を目指す動きと、その時代のコンピュータ機能を利用して人々の生活や企業の生産活動の向上を目指す動き」が並行して進んでいったことを思い起こします。
その後、計算機の性能はスパコンの時代に入り、現在はスパコン「富岳」の例に見られるように計算速度はエクサ級(1秒間の計算回数が100京回)のスパコンが最先端となっています。同時に記憶容量もどんどん増えて、ビッグデータのストレージから有用なデータマイニングが可能になっています。
検索エンジンはGoogleなどに代表されるように、私たちの生活の色々な場面で便利に使われるようになりました。一方、大規模言語モデルの性能が向上し、とうとう昨年(2022年)にはChatGPTがリリースされ、現在、議論百出の状況に至っている状態です。
これ以降は、私の個人的な意見です。
1. マイコン搭載の機器が便利だと言って使ってきたのと同じように、便利だと考えるなら使ったらよい。
2. 但し、倫理的な判断は各人が厳密に行って、教育・研究の現場で悪用しない。
3. 企業(大きく言えば国家)の戦略決定のための判断材料として、効率的にAIを使うことはあり得るであろう。
4. 但し、戦略・政策決定の判断は人の判断力が重要であり、AIはあくまで材料提供の手段であるべきである。
最近、以下の本を読んでみました。
「AIが答えの出ない問題に答えてみた」著者:Catchy 発行㈱クロスメディア・パブリッシング (2023) ISBN978-4-295-40808-6 (Catchy は「AIライティングCatchy(キャッチ―)」の省略形です)
内容は、古今東西の有名人20人に質問したとして、Catchyが答える形式になっています。例えば、リンカーンが社交の立場から、「意思決定能力を高めるコツはありますか?」と言った質問に答える場面、マザーテレサがお母さんだったとして「大学に行った方がいいでしょうか?」と言った質問に答える場面などがあります。読んだ印象では意外と穏健なバランスの取れた答えが返っていると思います。学生がレポートの材料として読む場合は「可もなし、不可もなし」と言った程度の回答です。ただし重要な戦略・政策決定の判断材料としては物足りないと言うのが率直な感想です。
この分野は今後も急速な発展を遂げると思いますが、現状では人の意思決定の補助材料に過ぎないと思います。AIそのものが意思を持つようになる時代はSFの世界だけなのかどうか、今後も注意して見て行きたいと思います。 (USI)
工学系でコンピュータに近いところにおられたのでお詳しいのでしょうね。
私は出来れば、生成系AIとは何なのかを自分なりに理解して、使ってみる事だと思います。
高齢者であっても。
何でもどう言葉を選んで質問するかで、プロンプターという役割が重要になっているとのことです。これにより大きく答えが違うとの事。
要は、卑近な言い方をすると「国語力」が大事という事でしょうか?
KNKさん、日本のデジタル化への遅れ、確かに我々年代層(すべてではないが)の牽制が影響しているのでしょうね。マイナンバーカードを作るのにあれだけのポイントを付与しないと、それでもシステムで不具合が出たり、事件があったりで、デジタル化対応に不安感を持ちながら、前に進むのに躊躇しているのが現状でしょうね。でも、紹介の書籍では(高価なので購入してませんが)その不安感を払拭するこれからの時代を説明しているのでしょうね。会員のHYSさんから、「画像生成AI」の事例をご紹介いただきました。国もチャットGPT導入を政策として進めているようですが、現場の技能取得遅れが指摘されているようです。学校現場では、教師に相当の困惑があるようです。
私は、以前、6年前に出版された「人工知能と経済の未来」~2030年雇用大崩壊~(新書本)井上智洋著を読んでいました。今、振り返ってみると、思いは、彼が最後に、経済学者ケインズの言っている言葉を紹介していることです。「われわれはもう一度手段より目的を高く評価し、効用よりも善を選ぶことになる。われわれはこの時間、この一日の高潔で上手な過ごし方を教示してくれることができる人、物事の中に直接の喜びを見出すことができる人、汗して働くことも紡ぐこともしない野の百合のような人を、尊敬するようになる。」「ものごとの中に直接のよろこびお見出すこと」とはバタイエのいう至高性の他なりません。ケインズのこの予言が成就する時、有用性の権威は地に落ちて、至高性が蘇るでしょう」と結んでいる。これから、人は有用性(デジタル)を享受しながら、余暇の時間(アナログ)の楽しみを見つける。ということを言っているのだろうと思う。
さすが既に関連の本を読まれていましたか。
AIに関しては、チャットGPTが出現した事で新しい局面を迎えた様です。
人類は懸念を持ちながらも、技術の進歩には逆らえず、私などはどうせ進むならどしどし進取の精神で取り込んでいこうと思って来ました。
特にインターネットが良い例です。今やネットが無ければ成り立たない社会になりました。弊害もたくさん出てきました。
これら技術と人類がどう折り合いを付けていくのか、私たちも参加しながら、見守って行くべきだと思います。
私のAIの使いこなしについては、やっとチャットGPTから使用の許可が出た所で、まだ使っていません。
じつはAIとは、どうやってその結果を出しているか、人間はだれも分からないとの事。そこが恐ろしい所です。
ネタはインターネットとの事なので、分かり切った事や答えが出ない事を聞いてもしようがないと思うので、どう活かして行くか考えどころです。
まず試してみる事が正解なのかも知れません。
先日紹介した、アドビ社のfireflyもGoogle社の検索機能に搭載される予定との事。検索もどう進化して行くのか楽しみでもあります。
AI関連本としては、チャットGPTをどう使うかの本ばかりで、この様な概略の解説本は貴重です。